ログハウス風の木製小屋は、外壁を無垢の木材とすることが多いです。
屋外に面する木材を長持ちさせる上で、メンテナンスがとても重要です。
いつも人が住んでいる環境と違い、空き家や長期間放置される別荘などは、屋外に面する木部の痛みが早く、通常の住宅よりも注意が必要です。
そんな木製小屋のDIYリフォームは、木部の塗り直しが基本です。
木部リフォームの基本、再塗装(塗り直し)

木が腐る原因は、主に細菌や害虫の食害で、これを効率的に防ぐには塗装の塗り直しが最も有効です。
条件によりますが、1年に一度の木部再塗装をおすすめします。
塗料により耐用年数が違います。
再塗装をしない時でも、1年に一度は塗装面を清掃するようにしてください。
汚れを落とすだけでも腐朽菌の付着数が少なくなり、虫害リスクも抑えることができて、木部耐久性が大きく変わります。
なぜ再塗装が必要なのか?
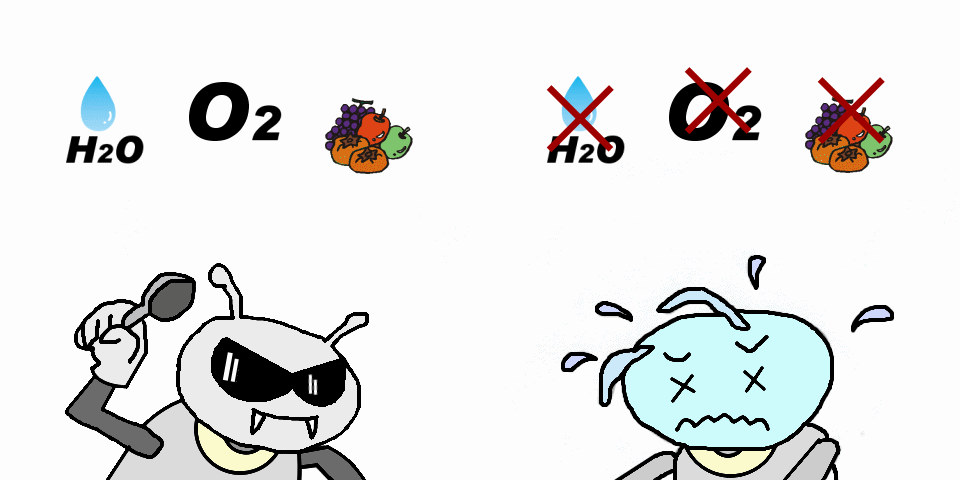
木部塗装は含まれる成分や効能により、塗膜や含浸薬剤のはたらきで「酸素、水、栄養」を遮断します。
しかし、日照や風雨にさらされ、年月の経過で劣化がすすみ、次第に効果が薄れてきます。
そのため、再び塗装することが必要なのです。
屋外に放置された木板裏には、ミミズや微生物が生息していますが、彼らが木部を分解します。
水分や酸素が豊富にある地上に置いた状態が、木材を最も腐朽させる環境です。
気温上昇により生物活動が活発化する夏の前にメンテナンスしましょう。
木が腐るメカニズム

木部腐朽は錆などの化学反応(酸化)とは違い、菌や虫の食害が主です。
木材腐朽菌や木食虫類は「酸素(O2)、水(H2O)」と「栄養素(木材)」の三種が揃うと分解(食害)活動が活発化します。
「水車」や「木船」は意外に朽ちないのは、酸素か水が欠乏し腐朽菌活動が抑制されるためです。
空中では水が少なく(乾きやすい)水中や地中では酸素が欠乏します。
反対に地上面では「酸素、水、栄養素」の三拍子が揃うことで最も腐朽が進みます。
そして、腐朽が進み始めた木部を好む白蟻やスズメバチなどが、さらに木部腐朽を加速させることになるのです。
こまめな再塗装でリフォーム効果
木部塗装による塗膜は、上記の腐朽三要素を遮断します。
しかし、風雨で塗膜が劣化するので短期間でリフォーム再塗装することが大切です。
清掃で汚れを取り除くだけでも効果があります。
屋外の木部はこまめな再塗装や清掃が高耐久の決め手です。
防腐効果と価格が比例する塗料

高価な塗料の方が耐久性が高いですか?
こんな質問をよく受けます。
塗料により、確かに防腐性能の差があります。
14リットル単価が¥15,000~¥30,000と、2倍の価格差がある木部塗料も存在します。
私の使用感ですが、防腐効果の継続期間も約二倍と考えて良いと思います。
(一部の自然塗料などを除きます)
価格と防腐性能は比例してるような気がしますがどうでしょうか?
軒先にご注意

軒先のせり出しが小さいと、壁や壁下が雨水で長時間濡れて腐朽が促進します。
軒先自体も腐朽が早い箇所です。
この部分に水が滞留しないように、水切り金物などで対処しましょう。
「雨どい」は雨水の打ち返しを防止できて、壁や床部の木材腐朽防止に有効です。
できるだけ木部は濡らさないようにしましょう。

うす塗り、塗りにくい所から
塗料の厚塗りは、ひび割れや色ムラの原因です。
塗料はうすくのばして、何回も重ね塗りするように作業します。
塗り忘れを防ぐため、細かい場所や塗りにくい場所から塗りはじめ、正面や広い面は最後に塗装します。
塗料性能がおちるので、気温が5℃以下の時は塗装作業をさけましょう。
廃棄は下水に流さず紙や布にしみこませ、一般ごみとして処理します。
用意するもの

ハケと容器
ハケは大小2種類あると便利です。
塗料を入れる容器はペットボトルでもOKです。
塗料
ムラ防止のために、缶底にたまりやすい塗料成分を撹拌します。
缶を逆さまにしたり、棒などでよくかき混ぜましょう。
開封後は性能がおちますので、使い切るようにご用意ください。
カビや古い塗膜が残っていると仕上がりが悪くなりますので、塗る面の下地掃除をして、塗りたくない所はあらかじめマスキングをしましょう。
ステイン系の塗り直し手順
- 汚れやカビを取り除く。
- 塗装面を水やうすめ液できれいにして乾燥させる。
- 最下部や隙間、ドア枠や窓などの塗りにくい所から吸い込ませるように塗る。






ペンキ系の塗り直し手順
- 2色の場合は、サブカラー材(隅木、破風板など)をはずす。
- ステンレスたわし等で劣化した塗膜を落とす。
- 細かい部分、上部(高い所)から再塗装。
- 2回塗りが基本なので1回目がよく乾燥してから2回目を塗り、乾燥させてからサブカラー材を取付なおして再塗装完了。
(↓)写真の塗料はアサヒペンの「バリューコート(つや消し・空色)」を使用してます。






まとめ、塗り直しこそDIYで
木部の塗り直しは、腐朽を防止し、木材の耐久性に影響します。
塗装作業を業者に依頼すると、意外と高額になります。
それは、リフォーム請負工事として受注すると、品質保証や安全対策など、事業者としての責任が一因にあります。
自分で小屋を建てたセルフビルダーは、自分で塗装作業しましょう。
住宅だってDIYで木部塗り直しできる
木部の塗装作業そのものは、それほど高度な技術を必要としません。
「多少塗料が窓にはねても拭けばいいや…」
「色ムラは自己責任なのでしょうがないや…」
という方は、外壁が木材なら住宅でも、自分で塗装リフォームしてください。
ただし、高所作業や電気配線近くなど危険を伴う箇所の作業は、無理せずプロの業者に依頼しましょう。
自分でできる部分は作業して不可能な箇所だけ塗装作業を依頼すると、見積価格を抑えることができます。



コメント