古い木造小屋は、何となく色あせてきて寂しげな印象になります。
しかし、塗り直しのリフォームをすると、まるで新築のように印象が変わります。
木部塗料の性能は年々進化しています。
防腐持続年数が長くなり、色数も増えてきました。
扱いが簡単な水性塗料も油性塗料と性能差がなくなってきました。
小屋作りに欠かせない「塗り直し」について、小屋のリフォームと捉えて考えておきましょう。
ペンキ系とステイン系を理解しておく
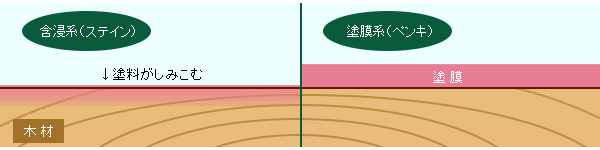
木部塗料は大きく分けて「ステイン系」と「ペンキ系」に分かれます。
ステイン系は薄透明塗装で、木部素材表面に半透明塗料を含侵させるタイプです。
塗装面の下地の木目が少し見えたまま仕上がります。
ペンキ系はベタ塗りで塗膜面を作り、木部をコーティングするタイプです。
下地は完全に見えなくなり、まったく違う色に塗り替える事も可能です。
防腐の効果は?
塗料の防腐効果は、メーカーや商品により品質性能にややばらつきがあります。

ペンキ系とステイン系ならどちらが長持ちするの?
どちらの系統も防腐効果の持続性に大きな違いが無いように思えます。
商品ごとに性能差があり、再塗装の頻度が防腐効果に大きく影響します。
塗料はリッターあたり2~3倍の価格差があったりします。
防腐性能の持続性は値段に比例しているように思います。
これまでも20種類以上の塗料を使用しましたが、高価な塗料はそれだけの価値があると実感しました。
ステイン系で明るい色は劣化が目立つ

合板材に明るめのステイン系塗料を塗ってから3年ほど経過した状況です。
黒ずんでいるのは、カビの繁殖が進んでいます。
長期間、塗り直しをしていないと、明るい色は下地木部の変色によって色劣化が目立ちます。
こまめに塗りなおすのがおすすめです。
木材の下地色変化が、色あせた感じになる

新品の木目はキレイですが、屋外で紫外線の影響を受けると数年で変色します。
樹種にもよりますが、だいたい二年ほど屋外に放置していると、画像のように変色します。
塗装下地である木材の色変化が色あせた感じの原因で、薄めの淡い色や明るい色はそれが顕著に目立ちます。
色あせが…、白色系ならペンキ系を

ステイン系塗料で白色や淡い色を選ぶと、数年で色あせを覚悟しなければなりません。
塗りなおしても下地の色が変化しているので、新築時と同じ仕上がりになりません。
ステインの「クリア」を塗装する方もいますが、これは完全に退色します。
白系で仕上げたいときは、塗膜をつくるペンキ系塗料の方が退色が気になりません。
塗り直すと新品のように生まれ変わるので、白系はペンキがおすすめです。
変わってて面白い、木造小屋の外壁
はっきり言って小屋は塗装でキマります。
個性的で面白い塗装仕上げもあります。
カラーリングを考えてから色の設計するのが良いでしょう。
イラストを描いた外壁


ペンキ系は塗り直しができるので、遊び心があってオンリーワンな外壁になります。
定期的に描きなおすと、楽しく塗り直しリフォームができます。

セルフビルドの楽しみ方で、木製外壁ならではのイメチェンできる小屋です。
ステイン系とは違いペンキ系なら下地が消せるので、濃い色から白系に塗り替えることもできます。
軍用ではありません、カッコイイ小屋ベース

地味なカラーほど小屋の存在感が増すような気がします。
ペンキ系のライトグレー1色で仕上げた小屋は、地味ですが周囲の自然景観とよくマッチします。
軍用格納庫ではありません…。
外壁材が一枚ずつ違う多色の外壁


外壁材を一枚ずつパッチワークのようにそれぞれ色を変えています。
外壁材取付前に塗装する方が、マスキングの手間がかからずキレイに仕上がります。

高い人気のウォルナット(濃い茶色)

ステイン系の人気第一位のカラーは、濃い茶色のウォルナットです。
同じメーカーで同じ製品でもカラーによって防腐効果がわずかに違います。
濃いカラーの方が防腐効果で少しだけ長持ちします。
サブカラーに白系を使うと、仕上がりの雰囲気が少し変わります。
塗り分ける時は、ドアや窓などの開口部のカラーも決めてから計画しましょう。
カラフルな海外では色設計する
よく見かける海外の小屋は、配色センス、イラストともにデザインが優れてます。
単なる防腐の為に塗装しているのではなく、どちらかというと配色やイラストなどで小屋をアピールしているようにも見えますよね。
よくみるとテキトーにカラーを選定しているのではなく、かなりこだわった配色です。
塗装前に「色設計」をして、仕上がりをよく考えているのでしょう。
PCなどで色合わせを繰り返して小屋の色設計に時間をかけたいですね。

よく見ると配色もパーツごとに細かく塗り替えられてます。
おそらく塗装作業もかなり手間がかかっています。
カラーの組み合わせもよく考えていますね。
「○○色にする…」としても調色をかなり検討していますね。

まとめ、時々カラーリフォームを
小屋やガレージは、外壁カラーによって仕上がりの印象が大きく変わります。
色と色の兼ね合いや、どこをどう塗るかの塗り分け、塗装作業の丁寧さも仕上がりに影響します。
塗り直しは防腐効果が高まり、木造の耐用年数を伸ばします。
たまに小屋の外壁色を変えてイメージチェンジすれば、塗りなおし回数が増えることになり、防腐効果が高まり小屋が長持ちします。
塗り直しすると新築時のようにキレイになります。
DIYで小屋作りは大抵平屋なので、高い足場を必要としません。
少しの準備で気軽に開始できます。
防腐のためにもリフォームを兼ねてカラーチェンジの塗り直しを、楽しんでもらいたいものです。



コメント